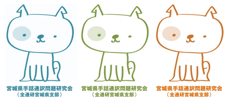2026/02/25
ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026で日本選手団が健闘しています。NHKは今回も開会式や閉会式の様子を手話通訳付きで放送しています。デフリンピックを含め、ろう者による手話通訳を目にする機会が増えましたね。全日本ろうあ連盟は、ろう者による手話通訳に関する検討を続けています。今年度は、モデル講座を実施しています。他にも養成と派遣に着手する自治体も出てきました。
CO通訳(ろう者と聴者が協働で行う通訳)は単なる役割分担ではありません。聴通訳者が音声言語から手話へと変換し、ろう通訳がそれをさらに自然で理解しやすい手話へと再構築する。その逆もあります。そこには、言語的調整だけでなく、文化的・認知的な橋渡しが含まれています。ろう者ならではの言語力と言語外知識、聴者ならではの言語力と言語外知識の相互作用により、情報の質はより豊かで精緻なものになります。
しかし、CO通訳の効果は、ろう者と聴者が一緒にいるだけでは生まれません。そこに不可欠なのは、通訳者同士の信頼関係です。そしてこの課題は、ろう・聴という違いに限ったことではありません。
2026/01/27
私たちは日常的に、ことばでやり取りをしています。家族や同僚との会話では、「言わなくてもわかるよね」「察してくれるだろう」という感覚が、自然に働くことも少なくありません。また、実際にそれで通じることも多々あります。それでも、ちょっとした言い回しの違いで誤解が生じたり、思っていた意味と違って捉えられていたという経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。
同じ日本語を使っていてさえ、コミュニケーションは決して簡単ではありません。ましてや、異なる言語・異なる文化をつなぐ通訳の現場では、「わかりにくさ」や「あいまいさ」と日々向き合うことになります。
日本語では、はっきり言い切らず、含みを持たせる表現がよく使われます。相手に対する配慮であったり、場の空気を和らげるためであったり、その背景には人間関係を大切にする文化があります。その一方で、その「含み」をどう受け取るかは、受け手の経験や立場によって大きく左右されます。
ここでよく話題になるのが、「推論(すいろん)」と「忖度(そんたく)」の違いです。推論とは、発話の文脈や状況、これまでのやり取りなど、根拠を手がかりに意味を組み立てていくことです。
2025/12/27
2026(令和8)年の幕開けにあたり新年のごあいさつを申し上げます。
旧年中は宮通研にご支援ご協力いただき、誠にありがとうございました。新年も引き続きよろしくお願いいたします。
公益財団法人日本漢字能力検定協会が毎年募集している「今年の漢字®」2025年の第1位は「熊」(23,346票)、第2位は「米」(23,166票)でした。特に熊の出没件数は36,814件(12/12読売新聞より)と過去最高で、被害件数も過去最高となり、これまでにない異常事態だったと思います。これまで、温暖化による異常気象や漁獲高の変動なども懸念されてきましたが、人と獣の世界にも想定外の変化が押し寄せているのかもしれません。
さて、宮通研会員である私たちの2025年を振り返ってみましょう。
まず、2025年のトップニュースは「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が成立したことでしょうか。第2回宮通研学習会でも取り上げましたが、2010年から全日本ろうあ連盟が中心となり、手話言語法制定を求めて取り組んできた成果ですね。
2025/11/29
全通研のスタンスは「研究・運動」です。「研究」というと研究者と呼ばれる賢い人たちが行っているなんだか高邁な難しいことのように感じます。全通研の「研究」は「実践的研究」で、私たちの地域の課題について解決策を考えて実践し、その結果を分析して改善に向けるものです。「運動」とは動くことです。体を動かすことやものが動くこと、社会を動かすことも運動といいます。もちろん全通研の運動は社会を動かすことです。
「社会運動」というとデモや集会などを思い浮かべますね。なんとなく特定の人たちが取り組んでいるイメージもあります。しかし、社会運動とは社会の問題解決や変革をめざす動きのことですから、特別な人々だけがやっているわけではありません。
先日の学習会で「手話施策推進法」についてお話しした際、「では、私たちはこれから何をしたらいいですか?」という質問がありました。まさに、社会運動についての質問です。たとえば、ママ友との世間話の際に「手話って知ってる? 私、昨日手話サークルに行って手話勉強してきたんだよ」と話題にしてみるのはいかがでしょうか。
2025/08/26
今年の夏も暑いですね。(毎年同じセリフを言っているように思いますが) 宮城県でもうだるような暑さだというのに、なぜか、南方の用務ばかり続き、南方も南方であるマレーシアはクアラルンプールに行ってきました。
クアラルンプールは北緯3.12度と赤道に近く、熱帯雨林気候に属しています。平均温度は28℃前後で、夏は日本よりも涼しいかもしれません。日本との時差は1時間で、羽田空港からクアラルンプール国際空港までの飛行時間は7時間30分くらいです。昨年訪れたインドネシアも他民族国家でしたが、マレーシアも同様で、マレー系(70%)、中華系(23%)、インド系(7%)となっています。言語や文化、宗教もさまざまですが、それぞれを尊重しながら共存している国です。
さて、WASLI(世界手話通訳者協会)は4年ごとに「WASLI Conference(世界手話通訳者会議)」を開催しています。WFD(世界ろう連盟)との取り決めにより、世界手話通訳者会議と世界ろう者会議は、少し日程をずらして同じ都市で開催されます。世界会議の間の3年間は9つに分けられている地域ごとにさまざまな取り組みをしています。
2025/07/31
戦後80年という節目の年を迎えた今夏、改めて平和の尊さを考えています。第二次世界大戦の終結以降、日本は戦火を免れてきました。約90%の国民は戦争を経験していません。しかし、世界ではいまだに多くの人々が戦争や紛争の苦しみにさらされています。開始から3年経ったいまもなお、ロシアの軍事侵攻により、ウクライナでは日々の暮らしが破壊され多くの命が失われています。パレスチナでも、長年にわたる対立と暴力により、子どもたちは平和を知らずに育っています。
戦争は人々の尊厳を奪い、未来への希望を閉ざします。私たち一人ひとりが「遠くの国の話」として無関心でいるのではなく、戦争によって失われる命や生活に目を向け、共に平和を願い、行動しなければ平和は維持できません。人間は言葉を持っています。対話や相互理解を重んじる文化を育み、暴力ではなく協力によって課題を解決する社会を築きたいと声を上げていかなければなりません。世界のあちこちに戦争の悲劇を繰り返さないための博物館やモニュメントが造られています。それらの施設を残した人たちの想いを今一度共有しなければならないのではないでしょうか。
2025/06/27
2025年6月18日「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」が成立しました。全日本ろうあ連盟は2010年から手話言語法制定推進事業を開始しました。手話の認知を進め、公私の領域で手話を自由に使用できる豊かな社会の実現を目指して、法整備を求める取り組みを続けてきたのです。『手話でGo』などのパンフレットを発行しては法律の意義や内容を周知し、自治体への働きかけにより、国内すべての自治体議会が手話言語法制定を求める意見書を採択しました。海外に出かけては手話言語法を調査し、国内では手話言語フォーラム等を開催し、手話言語条例制定を働きかけ、世論や国会議員を動かしてきたのです。手話言語法制定推進運動本部が考案した「日本手話言語法案」もありましたが、今回は、議員連盟と共に検討した「手話施策推進法(案)」が第217回通常国会に上程され、可決・成立の運びとなりました。当初希望した名称にはなりませんでしたが、最初の法律案で謳われていた五つの権利(①手話を獲得する ②手話で学ぶ ③手話を学ぶ ④手話を使う ⑤手話を守る)は、手話施策推進法にも盛り込まれています。
2025/05/29
近年、「ダイバーシティ(多様性)」という言葉をよく見聞きするようになりましたね。ダイバーシティとは、一人ひとりが持っている違いを認め尊重しようという考え方のことです。日本人は同質性を好む傾向がありますので、多様性を受け入れることはハードルが高いかもしれません。しかし、私たちはろう者や手話と出会い、ろう者のことを受け入れてきました。まさに自分と異なる人たちや言語を理解し受け入れようとするダイバーシティを実践していると言えます。また、宮通研は会員の属性やバックグランドも多様です。組織の構成員が多様だと、その組織の感性や実行力に幅と奥行きが生まれます。しかし、自分とは異なる意見や異なる行動は直感的に否定しがちです。そのようなとき、イントラパーソナル・ダイバーシティ(個人内多様性)を考えてみてはどうでしょうか。自分自身の中にもいろいろな側面があり、均一ではないことに気づきます。自分で自分の多様性も認めたい。ならば他の人の多様性も認めて、お互いにその力を発揮すれば百四十人力の組織になるのではないか、などと最近にやにやしているところです。
2025/04/25
4月の全通研は全国各地で支部の総会や代議員会ブロック別会議などが開催され、大忙しです。宮通研も4月12日に2025年度定期総会を終え、新しい年度がスタートしました。年度替わりには転入や転出により、宮通研会員にも移動があります。宮城を離れた皆さま、ぜひ移動先の全通研支部でも活動を続けていただきたいと思います。宮城に来られた皆さま、これまでも宮城っ子だった皆さま、新年度も宮通研ライフをお楽しみください。宮通研は会員の皆さまと運営委員が一緒に作っていく会です。どうぞよろしくお願いいたします。
2024年度は全通研創立50周年ということで、50年間を振り返り、50年間を学ぶ行事や話題が多かったと思います。定期総会のあとに行われた特別企画でも、「全通研とわたし(たち)」と題して、全通研と宮通研と皆さんの活動の歴史を振り返る時間をもちました。
ここで、全通研クイズです。全通研の生年月日はいつでしょうか?
答えは、1974年6月3日です。ヒトの妊娠期間は280日(40週)ですが、全通研の妊娠期間は2年間ありました。ゾウ並みです。・・・
2025/03/26
(Noricoda in 宮通研 ミニ)
皆さんにとって一年の始まりは何月でしょうか。日本は1873(明治6)年に太陽暦を導入してから、1月1日が年の始まりとなりました。しかし、官公庁や学校などは、4月1日を年度の開始日としています。これは明治政府が財政制度を整備するために欧米の会計制度を参考にし、イギリスの会計年度(4月1日~翌年3月31日)に倣い、1886(明治19)年から会計年度を4月始まりに統一したからです。それに伴い教育制度も4月始まりになりました。また、日本では農閑期の春は子どもを学校に送り出しやすい時季でもあったようです。一方、欧米の学校は9月始まりが多いですね。それはヨーロッパの収穫時期が夏で、それが終わった後に学年がスタートしていたことの名残です。昔は、子どもも重要な労働力で、暮らしと年度が密接に関係していたことがわかります。
4月といえば、白一色の世界に花や樹々の色が戻ってくる季節です。昼の時間のほうが長くなり梅が咲けば春の訪れを感じます。桜の開花は新たなスタートを祝福しているかのようです。日本人にとって「春」はまさしく一年のスタートの季節ですね。